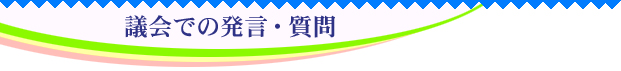■定例会一覧■
クリックすると各定例会の目次にリンクします
●2011年度
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2010年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2009年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2008年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2007年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2006年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2005年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2004年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2003年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2002年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2001年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
●防災対策およびピロリ菌検診について−浅子委員(2011年10月5日)
○浅子委員 私は、防災対策について伺います。
第一次避難所は、区立の小学校、中学校、あと都立高校と他の私立の学校となっています。東日本大震災でも、ピーク時には小・中学校622校が避難所として使われ、大変重要な役割を果たしたと言われています。それでは、第一次避難所の防災機能は、実態はどうなっているのか。
国立教育政策研究所というところが調査したところ、避難所としての運営マニュアルを作成しているというのが32.7%、今回の震災では、避難先の学校で備蓄食料や暖房設備の不足などの課題が浮上してきたと言われます。また、学校施設の設計時に避難所として使うということを想定していたというところは、4割にとどまったという調査の結果になっています。
足立区では、いち早く学校を避難所として位置付け、整理をしてきましたが、大災害を体験し、我が党が6月議会でも指摘してきましたが、課題をどう捉えてどう改善を図るのか。また、学校施設は設計時から避難所として利用することを想定してやっているのかどうか伺います。
○災害対策課長 避難所につきましては、今ご指摘ございましたように学校施設を中心に利用させていただいております。
課題としましては、数等がもう少し増やせないかどうかということの検証、あるいは運営におきまして、住民の方々のお力をおかりしているものですから、そちらがうまく運営できるように避難所のマニュアル等の改善を進めているところでございます。
○浅子委員 私も、3月11日は小学校に行きまして学校の先生やなんかと、帰宅困難者が中心ですが、受入れましたが、本当に大変な事態だったんですね。もっと増設することとか、運営協議会の行動の流れというんですか、それがきちっとできていなかったのかなというふうに現実に際して感じた点です。
災害時の要援護者対策を実態に即しきめ細かく
次に、要介護高齢者や障がい者とは、災害時において的確な行動がとりにくくて、地域住民や関係機関等による支援が必要である人のことで、自助、共助はもちろん、公助がどうしても必要だということで災害要援護者と言われています。
我が党の代表質問でも、要援護者については、安否確認のマニュアルはあるが、生存を確認した後の対策の充実がないと。その充実を求めたのに対し、災害時要援護者防災行動マニュアルの中で要援護者に合った対応を記載している。また、各要援護者に合った援助ができるように各障害者団体等の話し合いを持っており、今後とも継続的に協議していくと答弁しているんですね。
その答弁にあった「災害時要援護者防災行動マニュアル」というのは、これですよね。(実物を示す)皆さんもご存じだと思いますけれども、これは二つに分かれていて、一番最初が要援護者の共通の行動マニュアル、2章目が要援護者別の行動マニュアルというふうになっているんですね。
私、中身を見てみたんです。例えば精神障がい者とか、身体障がい者とか、妊婦さんとか、介護高齢者とか、別々にきちっと行動マニュアルがありますけれども、例えば災害時要援護者行動マニュアルの身体障がい者、とりわけ音声、言語機能又はそしゃく機能障がい者、このページには二つのことが書かれているんですね。
一つには、事前の備えとして、(1)笛やブザーなど自分が助けを求めたり安全を確保したりするために必要なものを身に付けます。2点目、筆談用ホワイトボードとそれに使うペンを備えておきます。括弧して、雨天時に使用可能で何度も繰り返し使用できるものが望ましいと書かれています。2点目には非常用持ち出し用品、携帯用会話補助装置を使用している人はバッテリーの予備を非常用持ち出し袋に入れておきます。栄養チューブセットなど食事のための器具を非常用持ち出し袋に入れておきます。この二つが書かれているんです。
これでいざというときの行動マニュアルになっているのかなと、私これ読んで思ったんです。用意しましょうねというのはなっていますけれども、じゃあ用意してどうするんですかと、それが書かれていないんですね。
身を守るために避難しましょうということも、一言も書いてないんです。これで本当に行動マニュアルと言えるのでしょうか。
○災害対策課長 先ほど浅子委員の方からご発言ありましたように、全て公助で賄うことができないということで、まず自助の部分をこのマニュアルの中では重点的に書かせていただいております。今読んでいただいた部分もその部分でございます。
合わせまして、やはり関係団体、例えば福祉ですとか医療とか、そういった方々の関係なくしては要援護者の支援というものはできませんので、そういった仕組みも合わせてつくっていくことが課題だと考えております。
○浅子委員 そうです。仕組みをつくることが凄く課題だと私も思います。
要援護者が災害時に不安になって一番やってもらいたいことは何だと思うでしょうか。自分が安心できるところに避難をしたい、それが一番こういう災害時に感じることなんじゃないかと思いますけれども、高齢者などを担当している福祉部の方、どのように考えますか。
○福祉管理課長 災害時に障がいの方は、特にたくさんの不安をお持ちだと思います。一番は情報だと思います。情報がそれぞれの障がいでバリアがございますので、そういったところできちっと情報が伝えられるように、また、日頃支援をしてくださっている方が仮に介護等で一緒にいられるようであれば、そういったことも支えになるのではないかと考えます。
○浅子委員 そうですね。だから、代表質問でも、生存を確認した後の対策の充実が大切だと求めたんですね。
現在の避難所マニュアルでは、要援護者も、まずは第一次避難所に行きなさいとなっていますよね。小・中学校の体育館に行くようになっているんですけれども、本当に介護の必要な高齢者を、災害のときわざわざ一次避難所に連れていくのが良いことだと思いますか。
災害時、状況いつもと違いますよね。そういう中で、スムーズに行動できない。普段だって大変なのに、まして精神障がいとか知的障がいの方々なんか、パニックになってしまうのは当然です。そういうときに災害要援護者については、誰が考えても、最初から第一次避難所に行くんじゃなくて、一番安心できる第二次避難所に行ってくださいというのがいいんじゃないかと私は思うんです。
私の家にも要介護3の高齢者がいるんですね。つえを使って、いろいろなところを触りながらゆっくり、ゆっくり歩くんですよ。それが時間かかかるんですね、普通でも。それがこういう災害時のときに、やっと歩いて第一次避難所に行ったら、今度あなたは第二次避難所、要援護者なので次はあっちへ行ってくださいなんてたらい回しにすることが、本当に要援護者にとって良いことなのかと。私は、良いことだとは考えられないんですけれども、いかがでしょうか。
○危機管理室長 災害時におきましては、要援護者の方、それからその災害によって要援護者状態になってしまう、けがをされるという方々もおられます。そういったことを、ひとまず防災計画の中では、第一次避難所が速やかに立ち上がりますので、そちらに行っていただいて、そこで切り分け、トリアージをするようなこともありますでしょうし、また、その震災の状況によりましては、第二次避難所が速やかに立ち上がれば、そこに誘導することも可能かもしれません。
いずれにしましても、今回の東日本大震災を受けて、我々が行政としてのマニュアルであるとか制度であるとか、そういったものを今全力で見直している最中でありますので、今浅子委員のおっしゃったようなことも含めて、福祉部門とも協議しながら改善に向けて対応してまいりたいと思います。
○浅子委員 時と場合によっては、直接第二次避難所の方に行ってもらうということもあり得るということで、これからマニュアルとして検討していくということでしょうか。
○危機管理室長 様々な状況、検討が必要ではありますけれども、そういったことも含めて検討してまいります。
○浅子委員 要援護者を大勢のいろいろな人がいる中に最初に連れていくんじゃなくて、最も弱者と言われる方々は、最も安全なところ、安心なところに行ってもらうというのが一番私はいいことだと思います。
避難所の整備と、具体的に災害時どう動くかのマニュアル、それに基づいた避難訓練、この三つを整えていくことが、今とても大切なことだと思いますけれども、いかがでしょうか。
○危機管理室長 マニュアルにつきましても、一回つくればそれで終わりということではありませんので、改善の余地ももちろんあるでしょう。それから、それを使った訓練がなければ、実際に起こったときには実働できませんので、そういったこともこれから検討しながら進めてまいりたいと思います。
○浅子委員 是非弱者を大切にということで、検討の一番の課題にしていただきたいと思います。
それから、増設ですよね。まだまだ足らないと、第二次避難所が。大体今でも要援護者が2万人ですか、もっといらっしゃるんでしょうかね。それに対して、8,000人ぐらいの収容の施設しか第二次避難所になっていないということで避難所の増設、それから備蓄です。今年からやっと始めたということですが、早急に備蓄の具体化を計画を持っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○災害対策課長 備蓄につきましては計画的に進めてまいります。先ほどの増設につきましても、先ほど公明党さんの方から、具体的なこんな施設はいかがだというような提案ございましたので、様々なところに当たりをつけてまいりたいと考えております。
精神障がい者と家族が安心できる避難場所の確保を
○浅子委員 ありがとうございます。それから、代表質問でお聞きしましたけれども、精神障がい者について、代表質問では、第二次避難所での避難生活は難しく、医療機関と協議の上での対応と考えていると答弁をしています。
そうしますと、病院にみんなが行ってくださいと言ったら、一体何人が病院に入れるのかと。現実から出発して具体的な想定が必要だと思いますが、いかがでしょうか。
○保健予防課長 精神病院五つございますが、自立支援法の精神の医療にかかっている方が9,000人以上おりますので、その方全てが一度に駆けつけるとなると、これは全く対応ができないということになろうかと思います。二次避難所というよりは避難所のバックアップ、避難所にもなり得るでしょうけれども、全ての方がそこに最初から押しかけるということではなくて、お薬を処方すればいい方は一次避難所でいていただく精神障がい者の方を想定しておかないと、全く対応できないということになってしまいます。
協議は、今後なるべく早く始めたいと思っております。
○浅子委員 家族の方は、本当に皆さんにも迷惑をかけて避難所に行くのも気遅れしてしまうというようなお話もあります。是非精神障がい者の方々も安心の居場所をきちっと確保するということで、積極的な検討をお願いしたいと思います。
本当に要援護者のことを考えるならば、事前にいざというときにここに避難をしてくださいと、第二次避難所を知らせておいて、その際に考えられる困難を想定して解決していくことだと思っています。
そうした考えに立てば、精神障がい者の方だって要援護者として適切な方策はとれると思います。家族が心を痛めるのではなくて、公的にいざというときに支援をすると。また、そのために障がい者団体の意見や要望を聞くことが大変に重要です。
例えばろう者の関係では、足立区ろう者福祉推進合同委員会と区との協定で手話通訳等を派遣する避難所が既にできています。
また、腎臓を患い人工透析をしている患者の方々も、積極的に要望を出して自分たちの命を守ろうとしています。
要援護者マニュアルは、真に要援護者の命を守るという立場でこれから改定するということでお願いをしたいと思いますが、最後にもう一度答弁をお願いいたします。
○災害対策課長 先ほどの団体との協議につきましては現在も行っております。本会議でも、そのように答弁させていただきました。その点については引き続きさせていただいて、マニュアルにつきましてもより良いものに改善できるように、引き続き検討を進めてまいります。
胃がんの早期発見に役立つピロリ菌検診を拡充せよ
○浅子委員 次に、ピロリ菌検診について伺います。
近年、がんによる死亡者数は年々増加して、現在、がんによる死亡者は毎年約30万人に達しています。日本人の3人に1人ががんで亡くなっていると。
がん予防の受診機会を保障して、早期発見、早期治療によってがんを予防して区民の命を守ることは、区として重要な課題だと思いますが、どうでしょうか。
○健康づくり課長 区として、区民の健康を守ることは課題だと思っております。
○浅子委員 区は、以前、胃のエックス線検査を行っていたんですね。ところが、ピロリ菌検査に変更してペプシノーゲン法と組合せて今実施しています。ところが、国では、ピロリ菌検診を胃の検診として認めていないと。
胃がんの患者の中で、ピロリ菌が陰性の人はまれで、1%程度と言われていて、ピロリ菌がなければ胃がんにはならないとまで言われています。そうした点では、胃の検診として、本当はそういう方向で国も認めて欲しいのですが、このピロリ菌検診、ペプシノーゲン法と一緒に組合せていくということで、拡大をしていくということを考えているでしょうか。
○健康づくり課長 現在、先進的な事例という検診として5年間試行として実施いたしております。現在、区が実施しておりますのは、ピロリ検診という名称になっておりますが、ペプシノーゲンとピロリを両方検査して、ピロリ菌が発見された場合除菌もセットになっているということで、広く拡大するにはちょっと課題が含まれております。
○浅子委員 課題が含まれているとおっしゃいましたけれども、実際にこのピロリ菌検診と検査、パイロットスタディですか、モデル事業やっていますけれども、そういう中で早期がんが発見された、ピロリ菌が発見されたという人数は、2000年から始めていますけれども、どんなふうな状況でしょうか。
○健康づくり課長 初年度20年度が12名、21年度が3名、22年度は6名となっております。
○浅子委員 もう1回、早期がんの発見は何人か教えていただけますか。
○健康づくり課長 今お答えしました数字は、早期がんの発見をされた人数でございます。
○浅子委員 すみません、ちょっと私が誤解しました。
そうしますと、ピロリ菌検診によって胃がんの早期発見に効果があるということが言えるんでしょうか。
○健康づくり課長 平成20年度は、がんの発見率が0.38%ということで、レントゲンのがんの発見率に比べれば非常に高い数値となっておりました。ただ、その後、2年目は0.14%、22年度は0.22%になっておりまして、確実に高いかどうかということまではまだ言い切れておりません。
○浅子委員 現在、受診機関は保健所だけで、1回につき85人と制限されていると。血液検査で済むもので、医療機関に拡大すれば、もっと気軽に受診する可能性があります。
また、24年度でモデル事業は終了しますが、我が党の代表質問に、検診内容、方法等について検証し、本格実施に向けて区民の方が受診しやすいよう検診内容や実施体制を含め検討していくと答弁しているんですね。是非ピロリ菌検診、これによって胃がんの早期発見ができる、効果があるということですので、医療機関にまで検診をする場所を拡大をして、是非早期発見のために充実をさせていただきたいと思います。