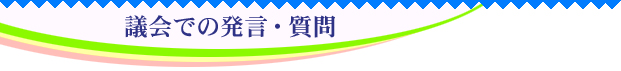■定例会一覧■
クリックすると各定例会の目次にリンクします
●2011年度
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2010年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2009年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2008年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2007年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2006年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2005年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2004年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2003年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2002年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2001年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
●地域経済活性化の諸施策前進を、UR住宅のエレベーター設置を求めよ−さとう委員(2011年10月12日)
地域経済活性化のため、区は区内業者への発注を増やすべき
○さとう委員 私は、中小企業のまちである産業振興策、これについて質問をさせていただきます。
足立区は、平成17年3月に足立区産業振興基本条例の全部を改定して、足立区経済活性化基本条例を公布しました。その際に日本共産党は、改正前の産業振興条例の本旨、目的であった足立区の産業においての重要な地位を占める中小企業等の振興、この位置付けが弱まり、目的からも消えたことを指摘して、地域社会の支え手でもある中小企業等の振興の基本となる事項を定めるようにということを加えることにより、区内の産業振興と活力ある地域社会の実現を図ることを目的にするということを提案いたしました。
この指摘は、今の産業振興の中で生かされているでしょうか。
○産業政策課長 平成17年の3月、足立区産業振興条例は足立区経済活性化基本条例とかわりました。当時の改正に当たりまして、足立産業プラン、この辺も検討してまいった足立産業会議というのが当時ございました。その辺の意見を見ますと……。
○さとう委員 質問にちゃんと答えて……。
○産業経済部長 最後の現在の経済活性化基本条例も、持って活力ある地域社会の実現を図ることを目的とするというところで結合されておりますので、さとう委員がおっしゃられた中身というのは、その中で包含しているというふうに思っておりますし、そういう観点というのは十分心掛けながら事業運営に努めているつもりでございます。
○さとう委員 私は、今足立区が、様々な取り組みをしていることを評価したいというふうに思っています。更に充実することを求めて質問をいたしますが、大阪吹田市では、地域経済の活性化を目指すとして、2009年4月に、市の産業振興条例を制定しました。この中身が、非常に私は足立区に役立つ内容かなというふうに思いましたので、次に、5項目上げますが、これを条例に加えていっていただきたいと思って質問をいたします。
まず、基本理念には、中小企業の発展をもとにというふうに書かれています。それから、条例の目的には、地域経済の循環及び活性化を図るとうたっています。そして、大型店は地域社会における責任を自覚してもらう。それから、大企業は中小企業との共存共栄を図ること。そして、市の役割として、まず、必要な調査を行い、産業施策の総合的かつ計画的に推進することというふうにあります。これらのことを是非生かしていただきたいと思うんですけれども、答弁をお願いいたします。
○産業経済部長 足立区内、大企業、ほとんどございませんので、なかなか適合しない部分はあろうかと思いますけれども、その趣旨というのは、確かに必要な観点だろうと思います。今すぐ条例を改正するつもりはございませんが、特に循環というんですか、区内企業の発展をさせていくというところの視点は、非常に重要なことだろうと思っております。
○さとう委員 吹田市では、産業施策の方針として、市内の中小業者の受注機会の増大を図るというふうにしております。仕事が欲しいという悲鳴を上げている業者にとっては、大変期待できる条例だと考えています。吹田市の官公需の地元発注割合、工事、物品、役務は、毎年のように低下しているそうです。工事の地元発注率は2000年度の金額ベースで75.2%あったものが、2009年度には27.2%にまで激減したそうです。そして、今物品の発注は、常に20%前後で推移しているということの厳しい状況だということです。
そこで、市の官公需を担当する職員は、地元発注を高めるため、物品購入で市内業者を優先するという試行をしており、当面、過去最高の46.7%、金額ベースで、それを回復したいとしています。地元商店街の役員さんからは、官公需の地元発注で仕事が出て活性化をすれば、めぐりめぐって商店街の活性化にもつながると、条例の目的である地域経済の循環及び活性化について期待をしているということです。
足立区としても、地元発注を高めるために、全庁挙げて取り組んではいかがでしょうか。
○産業経済部長 受発注の関係は総務の方で持っているところでありますけれども、そういう、今さとう委員がおっしゃられたような観点、経済活性化会議という庁内連携の会議をやっておりまして、その中で、受発注について、各所管の契約においても、そういう視点を考えてもらいたいということで徹底をしているところであります。
○総務部長 契約の担当としては、区内の事業者に発注をしていくということで、大型の事業の分離分割発注もそうですし、小規模な少額の発注についても、できる限り区内の事業者を活用していくと、このように考えております。
○さとう委員 どうぞ、よろしくお願いいたします。
吹田市には、市産業労働にぎわい部という部署があるそうです。そこでは、2010年1月、今後の市の産業振興策の基礎資料とするために、条例の市の役割としての必要な調査ということで、全事業所の実態調査を実施しました。その結果、1,565事業所、回答率20.8%から回答が寄せられ、その結果、特徴の一つが、売上高の減少ということです。9人以下の事業所の70%が売上減少と答えたということです。小規模事業所ほど厳しい状況にあるということが、はっきりとわかったということで、それに対して、調査が今後の施策に生かされるということなんです。
中小企業支援策を進めるためには、まず、このような実態調査が必要ではないかというふうに考えます。日本共産党区議団は、毎年、様々な団体と懇談をしておりますが、後継者対策が話題になりました。業者青年の実態調査をすること、それから、業者青年の技術、技能の向上につながる人材育成を図ること、それから、事業所系の円滑化を促進することなど、様々求められているところですが、後継者についての調査も含めて、様々な観点から実態調査を行うべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○産業政策課長 足立区におきましては、中小企業の景況調査ということで、件数……。これはずっと前から調査しておりまして、その中で、例えば経営上の問題点ですとか、重点的に取り組むべき中小企業として、物は何かということの中で、そういった例えば人材を確保するですとか、そういったことも含めておりますので、実態的な調査というのは実施しております。これを参考に、様々な施策を実施しております。
○さとう委員 景況調査では、なかなかあらわれない実態が、この吹田市は、ちゃんとした部署があって、そして、市独自が調査をしているわけです。目的、意識的に調査しないと、なかなか実態がつかめないと思いますので、今後に、是非生かしていただいてやっていただきたいというふうに思います。
○産業経済部長 地域経済活性化計画でも、つくるときに事業者の調査とかしています。経済活性化プランでも、商店街の調査とかしています。商店街の方でも、跡継ぎがなかなかいないというのが大きな課題だという認識はしております。そういう適宜、調査進めていくとともに、マッチングクリエーター等から情報を把握しながら進めてまいりますので、吹田に負けないように、状況の把握等を努めてまいりたいと思っています。
○さとう委員 その決意を信じまして、是非調査を目的、意識的にお願いいたします。
認可保育園建設で区内建設の仕事を増やし、新たな雇用につなげよ
次に、待機児対策は認可保育園の建設を柱にすべきということを考えながら、認可保育園の建設に、どれだけ地元業者の仕事おこしになるか、どれだけの雇用の拡大になるかということで提案させていただきますが、保育課に試算をしてもらいましたら、0歳から5歳までの100名定員の保育園、これの土地代を除く建設費用は2億4,000万円だそうです。この仕事は、区内建設業に回る仕事だと考えます。あと、備品としては、1,500万円かかるということで、これを小売店に分離分割発注すれば、多くの事業者に仕事が回るというふうに思います。
また、保育園に必要な職員、これは保育課に出していただいたのは、保育士が15名、これが正規職です。看護師1名、正規職、非常勤16名、この非常勤については流動的だというふうにおっしゃっていましたが、これは私が見るからには、最低限に必要な人数であり、園長先生、主任、栄養士、そして、長時間保育の対応、特別支援保育の対応、それから、用務主事さん、給食調理など、更なる職員が必要になると思いますが、これら全て新たな雇用につながるかと思います。
これについて、建設の仕事、それから、新たな雇用につながるというふう思いますが、いかがでしょうか。
○待機児童対策担当課長 さとう委員ご指摘の認可保育園につきましてでございますが、認可保育園につきましては、区の方針といたしましては、大規模開発地域などの特定地域に全年齢にわたって待機児童がいる場合というような形で建設を考えているものでございます。
○さとう委員 そんなこと質問しているんじゃないんです。これだけ経済活性化になるんじゃないですか、建設する仕事は区内の事業者さんに回るんじゃないんですか、雇用の拡大になるんじゃないですかって質問しましたので、その担当の方、答弁してください。
○産業政策課長 ある程度高額な建設に関しましては、それなりの資格とかが必要であるかと思います。区内の事業者の皆様が、それぞれ要件を備えておれば、その契約の段階での判断と思いますので、内容的には契約の内容かと思います。
○さとう委員 どこまでも、どこまでも、認可保育園はつくらないということを報告していただきたくないんです。ちゃんと、私は、これは経済的に効果があるでしょう、公共事業というのは、そういう効果を発するんですよっていうふうに質問しているんです。
それで、更に、例えば給食用の食材、備品を地元の商店街から買えば、一つの保育園で、どれだけの食材を使うか。これも地域の活性化につながるわけです。それから、100名の子どもたちを保育することによって、保護者が安心して働くことができて、買物に使えるお金、いわゆる可処分所得が増えれば、地域の活性化にもつながり、納税者にもなるわけです。これは、もう質問をいたしません。
このように経済効果というのは、一つの保育園をつくることによって、どれだけあるかということを私は言いたくて、この質問をいたしました。そのことをきちんと考えて……。いいです。答弁いいです。
区の公共施設や街路灯にLEDを、工事は区内業者に
次に、LEDの普及による区内業者の支援について伺います。
LEDの普及を全庁的に取り組んで、その仕事を区内事業者に発注すること。例えば学校、保育園等、民間も含めた公的施設は、休日、冬休みに工事ができるように、そして、近隣のまちの電気工事店と協議するなど、すぐに取り組んでもらいたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○学校施設課長 学校の照明に関しましては、LEDにつきましては、まだJIS規格が決まっていないというような部分もありまして、まだ導入については検討中でございます。
○資産管理部長 今回、本会議でもご答弁申し上げておりますけれども、全体的にLED照明に替えることができるものが、工事、そういうものを含めまして10%程度でございますので、電球自体で取替えるような形の簡易なものから器具の改修が必要になるものございますので、その辺、含めまして検討させていただきたいと思ってございます。
○さとう委員 そういうことの説明ならわかるんです。そして、その機材も、まだまだ、これから開発されると思いますので、それに合わせて早急に取り組んでいただきたいというふうに思います。
区内商店街は、相次ぐ廃業で街路灯の維持も大変になっています。そこで、LED化に支援をすること、これはやっているかと思いますが、同時に、商店街で維持しきれない街路灯は、区の街路灯としてLED化にして管理すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○道路整備室長 商店街灯を、廃灯をして区の街路灯ということは、そういうことはできます。廃灯等については、商店街でやっていただいて、その後は区の方で対応する、そういうことは可能でございます。
○さとう委員 要するに私がお願いしたいのは、商店街が、もう維持管理ができなくなっている、そのことの対応として、区がきちんとやってもらいたいという意味で質問いたしました。
鹿浜地域の買物難民対策を
次の質問に入りますが、買物難民のことについて伺います。
鹿浜は、もう本当に、鹿浜地域、次々に中型のスーパーマーケットができて、その影響で商店街はもう寂れてしまいました。寂れた途端に、この中小のスーパーが全部撤退していくという状況になりまして、鹿浜にとっては本当に身近なスーパーであった公設市場がなくなって困っています。要支援1の方、本当にヘルパーさんにお願いしていた仕事を、今度は、買物のために使わなければならなくなって、その点でも困難を期しています。
そこで、鹿浜の公設市場は、暫定的に店舗を利用できるように、区が責任を持って参加商店を募って、生鮮産品がそろうようにすべきだと思いますが、どうでしょうか。
また、足立区全体で、やはり買物難民の地域が出ているということですので、その調査もして、空き店舗の活用や移動販売ができるように場所の提供など、区が橋渡しをすべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○産業振興課長 まず、鹿浜の都住の周辺の買物支援でございますが、さとう委員ご案内のとおり、鹿浜の公設市場の方、11月にスーパーの方、倒産をいたしまして、そこの、区の所有部分になりました。エレベーターの設置工事に向けて違法増築のところを撤去、先月、撤去済みでございます。その後、3月の予算委員会のときに、撤去後、公募をかけて早急にスーパー再開をするというお話をさせていただきましたが、その後、耐震工事の補強の点検をした結果……。
○さとう委員 時間がないので、ごめんなさい。
買物難民のことで答えてください。
○産業経済部長 耐震補強があるんですけれども、その耐震補強前にでも、何らかの形で鹿浜の状況を改善するような取り組みを進めていきたいと思っています。
また、後段の区内全域の買物難民のことなんですけれども、具体的な情報としては、余りそれほど実態として入っていない。共産党の党要望で入ってきているぐらいでございますので、そういう情報を組み立てながら必要な施策を考えていきたい、こう思っています。
○さとう委員 共産党は、調査が進んでいるんです。地域の住民の声をとってもよく聞いていますので、たくさんの声が入ってきております。
区はUR団地のエレベーター設置を強く求めよ
それから、時間がなくなりましたので、公的住宅で、いろいろ聞きたかったんですが、一つは、エレベーターのことでお伺いさせていただきます。
区営住宅のエレベーター設置は、今年度、調査をして、設置の方向に進むということですが、都営住宅についても、都民の切実な要望で設置が進んでいます。ただ、店舗付き住宅については、区と東京都の協議が、なかなか課題となっておって、進んではいません。
私の質問は、UR団地のエレベーター設置について、住民の高い要望があるにも関わらず、都営住宅では設置が進んでいる四、五階建てでも、ほとんど設置されていません。東京都や足立区との協議も必要なくつけられるはずです。都市再生機構自体がやる気になれば、できることであると考えます。住宅・都市計画課長に伺いたいんですが、区民の立場に立って、エレベーター設置を強力に都市再生機構に求めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○委員長 住宅・都市計画課長。時間ですので、簡潔にお願いします。
○住宅・都市計画課長 エレベーター設置されていない住宅に関してのご要望ということで、URの方には伝えてまいりたいと思います。
○さとう委員 ありがとうございました。
本当に、区民が安心して住める住宅にと、公的住宅の増設、それから、安心して住める環境をつくっていただきたいとお願いをいたしまして、質問を終わります。