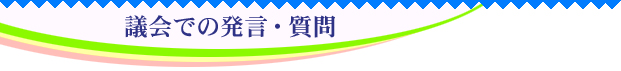■定例会一覧■
クリックすると各定例会の目次にリンクします
●2011年度
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2010年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2009年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2008年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2007年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2006年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2005年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2004年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2003年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2002年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2001年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
●区の防災対策条例改正、液状化対策助成制度創設を求める−針谷委員(2011年10月12日)
震災対策に対する区長の姿勢を問う
○針谷委員 私の質問で休憩に入ります。
私は、まず、幻となった区長挨拶、これについてお伺いをしたいと思います。
今定例会の区長挨拶、いわば所信表明演説ですけれども、事前に配られた文書が替えられたところがありました。その部分、ちょっと読んで見ると、東日本大震災、福島第一原子力発電所の事故から半年が経過した今もなお、ちょっと中略しますけれども、ここから先、当然のことながら区は住民に最も身近な基礎的自治体として強い責任感を堅持し、区として何ができるかを常に念頭に置いて積極的な対応を図ってまいります。この部分が消えたんです。で、台風15号の対応の話になったんですが、私は、この部分については、区長の挨拶から消えてしまったというのは非常に残念だなと思っておるんですが、改めてお伺いしたいんですが、この挨拶部分は、区長の政治姿勢としては、今も堅持していると考えてよろしいでしょうか。
○区長 限られた時間でしたので、間近な台風の対応の考え方に替えさせていただきましたけれども、この件については、全く揺らいでおりません。
○針谷委員 それで、防災計画の見直しについてお聞きしますけれども、日系グローカルが8月15日に人口10万人以上の都市に対して、自治体の災害対応力調査を発表しました。足立区は9位というランクにされております。これは区が、いち早く様々な対応を、私などに言わすと、放射線量の測定であるとか除菌(染?)対策、様々な対策をとった、これは我が党も評価をしております。しかし、これで、ぬか喜びしてはならないと思うんです。
防災対策の充実を私も求めるという立場から質問しますけれども、この記事の中で、名古屋大学の福和伸夫教授、この方がこう言っています。もともと23区は低地が低く脆弱な地盤が多いため、水害が発生しやすく地震の揺れに弱い。人口が密集しているため、一たび地震が起きると、家屋の倒壊や火災などで被害はけた違いに大きくなる。東京都が2008年にまとめた地震に関する地域危険度測定調査の総合危険度マップで見ると、23区は下町を中心に最も危険度が高い。西部の多摩地域とは危険度の差ははっきりしているというふうに指摘して、マグニチュード7.3の東京湾北部地震が発生した場合、政府の中央防災会議の被害想定では、死者は7,800人、建物被害は53万棟に及ぶと。国の推計では、今後30年以内に、そうした直下型地震が発生する確率は70%と高い。防災面から考えると、危険な地域に集中し過ぎているというふうに述べているんですけれども、東日本大震災を経験した今、こうした危険度が高い地域であるという認識はお持ちだろうと思うんですけれども、同時に、私、お聞きしたいのは、区の防災対策条例を、この東日本大震災で明らかとなった問題点を改善をし、補強するというふうな条例改正が必要になっているんではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
○危機管理室長 現在、3月11日の発災以来、できるものを速やかにやっていくという作業をしております。計画も、いわば、その条例に基づくものでありますから、その一環ということにはなりましょうが、そこで不足が見込まれれば、将来的に、今後は、そういったことも検討していくべきだと思います。
○針谷委員 条例改正、私は必要だと思っております。日系グローカルが、この調査をするに当たって、各自治体に33の設問をしております。それに、どう答えたのかという資料をいただきました。
そこでお伺いしますけれども、まず、地域防災計画の見直しの考えがありますかという答えに対して、一部見直すというふうに答えていますけれども、地震の想定についても、最大マグニチュードを引き上げるというふうに答えているんですけれども、震度7を想定した防災計画をつくるという考えはあるんでしょうか。
○災害対策課長 そのときの、たしか6月頃の調査だったと思いますが、お答えさせていただいたのは、まず区でやることを検討するということでお答えさせていただいております。震度につきましては、国の計画を待って、そちらの被害想定に合わせて想定を入れていくという考え方でお答えをさせていただいております。
○針谷委員 代表質問の答弁でも同様の、上位計画が示されておらず、区としては、今発生してもおかしくない震災に緊急に備えるけれども、上位計画が改正されたら、遅滞なく計画を盛り込んでまいりますと、こういうふうになっているんです。私、これは、ほとんど他の質問にも、上位計画が示されてからという消極的な、私は、態度ではないかというふうに思うんです。
先ほど紹介した、この日系グローカルのこれで1位となった渋谷区の区長さんが、こういうコメントを載せております。阪神大震災が教訓となっている我が区は、災害に強いまちづくり、地域防災力の向上を目指してきたと。災害対策総合条例を制定して、自主防災組織も100%になるなど、実も上げつつあると語っています。
私は、区長の政治姿勢で先ほど聞いたのは、区が住民に最も身近な基礎的な自治体として強い責任感を堅持して、区として何ができるかということを常に念頭に置いて積極的な対応を図っていくというふうにお答えをしていただいて、これ堅持していると、立派な、私は、姿勢だと思うんです。ところが、実際つくっている方は、区の下請け機関と言っちゃ言葉の言い過ぎかもしれませんが、実際に、積極的に、自ら足立区として何ができるのかという、やはり調査や研究や、やはりそういうものが不足しているんじゃないかと。
今地域主権一括法が出て、独自に積極的に自分たちが、こういうことが必要だというのを出して、国から出て、それにまた整合性を持っていくということは当然だろうと思うんですが、私は、求められるのは、そういう国待ちではなくて、独自に被害想定に基づいて防災計画をつくっていくことが求められていると思います。かつて区は、この阪神大震災のときに、そういうことをやった。多分、全国で初めてやったということが、この被害想定を震度7でやったというふうに思っております。
一つ一つ、具体的にお伺いをしたいと思うんですが、まず、津波を想定して、この答弁では、中高層建築物については、津波や水害時にオートロックの解除をお願いをして、区と協定を結ぶ必要があると思いますけれども、具体的には、この話は進んでいるんでしょうか。
○災害対策課長 他区の、今事例を調べているということで、検討中でございます。
○針谷委員 それも検討中なんだよ。答弁は、やるって言っているんです。全然、進んでいない。これは問題だと思うんです。
足立区でも液状化対策助成制度の創設を
次は、液状化についてお伺いします。これは、私が、毎回恒例で恐縮ですが、パネルをつくりました。
〔資料提示〕
○針谷委員 これは、東京都が作成した液状マップなんですが、この黄色い……足立区の地図のところです。黄色いところ、ちょっとグリーンと黄色が見にくくて、遠い方は恐縮ですけれども、この黄色いところが危険ということで、約半分ぐらい、足立区の地域では液状化が危惧されている地域。そこに、国土交通省の今度、外郭団体である地盤工学会というのが発表した東日本大震災における地盤液状化現象の実態解明報告書というのが出たんです。それが、この赤いのが、液状化が起きたところというので、私がちょっと、チョンチョンと落としてつくったんですが、これは、写真にもあります。こちらのとか、こちらの写真にもありますけれども、足立区の一次避難所となっている河川敷でも、土砂の噴出とか段差が見られる。また、西新井のアリオ前でも同様の状況があったと、それから、千住の西地域でも、下水道管などから、つなぎ目から砂が噴出して、周辺の家屋や道路の陥没化が見られたという報告を受けております。
足立区のこの対策として、今江戸川区が液状化により被災した住宅の改修工事費用の助成として、被災住宅の助成制度を新設しておりますけれども、これは修復費用の3分の2を助成するという、非常に画期的なものだと思っているんですが、葛飾区も同様の制度をつくるというふうに決めておりますけれども、区としても、こうした液状化対策助成制度をとる必要があると思うんですが、いかがでしょうか。
○建築調整課長 針谷委員ご指摘の江戸川区と葛飾区で、限定的な場所で10数件の液状化報告がありました。このため、東京都の被災者支援事業に基づく液状化被害の住宅のみの修復とか補助を始めることになっております。足立区におきましても、福祉部で、都の支援事業を活用して東日本大震災足立区被災者助成事業を立ち上げていく予定でございます。この助成事業の中で、液状化被害あるいは地震被害で半壊あるいは全壊の住宅に対し、補修、建設費に補助金により支援する内容となっております。
○針谷委員 それはやるということでいいと思うんですが、それは、今の話だと、国の制度をやるというお話は聞いているんですが、都の制度としてやると、新しい制度と、議会に報告した以外の新しい制度という意味ですか。
○福祉管理課長 区が、補正予算でご審議いただいて、お認めいただいたところでございますけれども、国としてはなかったところを都として補助制度を、住宅被災について補助制度を設けるということがございました。区としても行ってまいります。都の補助を2分の1いただきながら行ってまいります。
○針谷委員 これは大変いいと思います。是非引き続き頑張っていただきたいと思います。
内部被爆防止のためスクリーニング検査機器の導入を
次に、放射能対策についてお伺いをします。
児玉龍彦東大アイソトープ総合研究長が、衆議院の厚生労働委員会で国の放射線対策を厳しく批判したということで反響を呼んで、ネット上では大変もてはやされている人で、私も見ましたけれども、我が党区議団も、7月29日にシアター1010で放射線防護学の第一人者と言われている日本大学の野口邦和先生を呼んで講演会をやりました。
大変な反響でありましたけれども、福島原発から放射能物質の放出量は、ウランに換算して広島原発の20個分と言われています。しかも原発に比べて放射線の減り方が遅い、これセシウムのせいだと思うんですが、少量の汚染なら、その場の線量は考えられない。しかし、総量が膨大な場合に、粒子の拡散を考える必要があって、これは非線形という難しい科学だと言われておりまして、予測がつかない場所で濃縮が起きる。だから、稲わらに、牛肉のセシウム汚染が出たとか、板橋区で、お茶の葉っぱに汚染が出たとか、問題が次々に出てくると。最近では、ストロンチウム90も測定されております。都政新報でも、収束見えぬ流通追跡調査、牛肉の対象2,100頭にと、秋の米騒動に警戒感などと報道されております。ホットスポットに対しても、意外なところで高線量が測定されているというのが実態だろうと思うんです。
そこで、お伺いしますけれども、今回の汚染というのは、これまでの考え方では対応できない事態が今生れているという認識に、私は到達しているんですが、区の認識は、どうでしょうか。
○危機管理室長 これまでの対策では含み切れないという、そういったご趣旨が、どこを指しているかが、少しちょっとわかりませんが、これまで放射線対策というものは、国策の中で原子力開発であるとか、あるいは医療系放射性物質の扱いといったものに限られておりまして、一般の環境中に拡散されることはないとされておりましたから、各自治体においても、そういった対策事業についてはなかったわけであります。そういう意味であれば、これまでの対策の範囲には入りませんねというお話であれば、そのとおりですというふうに。
○針谷委員 そういう意味もあるし、また、新しい事態が生れているということを指摘したいと思うんです。
それで、子どもの放射線の内部被爆が問題になっていて、親からの学校給食の牛乳とか食材に不安の声が依然として強いと、牛乳を飲ませて欲しくないというような意見も聞いております。そこで、野口先生にも、食の安全を支えるために全量検査は必要ないだろうというふうに言っておりますけれども、サンプル調査は必要というふうに答えております。
江東区は、小・中学校や保育所、給食食材の放射線量を測定する検査機の購入をします。来年2月頃購入予定で、食材や調理済みの給食のスクリーニング検査が可能になって、費用は約500万円。都の補助金を活用していこうということですが、杉並区も同様の対応をしているということでありますが、これについて、区として、こうした放射線量を測定する検査機器を購入して、区民農園などの野菜も測定をできるようにするというような考えはないでしょうか。
○生活安全担当課長 内部被爆、食品の安全のことになるかと思いますけれども、今国の方では、産地の方で検査をしております。また、流通品につきましても、流通品の抜取り検査ということで行っております。そういった検査結果では、一部、基準を超えたりということはございますけれども、そういった物は流通の差止め等を行っておりますので、現在の今流通している物については、問題はないというふうに考えております。
○産業経済部長 足立区の農産物に関して、きちんと東京都の方で検査をしていただいておりますので、区民農園までやる考えはございません。
○針谷委員 東京都の健康安全研究センターというところが、放射能についての放射線基礎知識って出しているんです。今までのお二人の答弁というのは、このレベルに到達していないね。はっきり申し上げて、今身の回りの放射線をはかる調査は、文部科学省により全国規模で行われている。しかし、大事なことは、身近なところで継続して調べることによって、どのように変わってくるかを知ることができる。身の回りの放射量を常に把握していくことが、万一の時の事態を迅速かつ正確に把握することで重要だと。東京都の認識は、こうなんです。そちらの認識は違うのね。この差が、やはり区民の暮らしや、また健康を守るという認識の違い、私は、それではだめだろうと思います。
是非区は、私は機械を購入する問題は、是非やってもらいたい、検討してもらいたいと思うんですが、牛乳を委託をしても、江東区は委託をして検査をするということになっているんですが、そういうことも考えはありませんか。あるかないか聞いている、学校給食の牛乳。
○学務課長 現在、学校給食で使用しております牛乳につきましては、メーカー側で自主検査をしているという報告を聞いてございます。
○針谷委員 メーカー側に、それはお頼みにじゃなくて、区として、やはりその状況をつかんで、それは委託でもいいですよ。やるべきだというふうに主張して、とどめておきたいと思います。
私、次に、請願も出ておりますけれども、個人測定器を区民に貸出すということが可能になってきているというふうに思うんですけれども、この貸出しを受けた区民が測定をして高線量が出たときには、再度、区が測定をして、場合によっては除染をすると、こういう考えはございませんか。
○環境保全課長 ただいま測定器2台ございますが、毎日の測定に使っておりますので、今貸し出せる状況ではございません。
○針谷委員 区内に、足立区には放射線の個人測定器は、貸し出す状況じゃないどころが、150個以上あります。どこにあるか知っていますか。
○教育政策課長 現在、昨年度、理科の教科の変更がございまして、放射線測定機器、中学校の各学校の中に147台備えているところでございます。
○針谷委員 学校の教材で、私、校長先生や理科の先生に聞いたんです。一年中使っているわけじゃない、ほとんど、その理科の実験のときに使うだけということですから、これは、私は有効活用していく必要がある。
実は、私、地元の中学校に見せてもらって、その測定器が、どんな物か調べました。ドイツ製で、野口先生に見てもらいました。これは良いと、これはGM管の都政新報で言っている、いわば危ないチャイナ製の物ではないということで、これは使えますよという話を聞きました。
ですから、私は、有効活用をして、いろいろな、いわゆる開かれを使って、いろいろなことをやっているわけですから、学校の避難訓練のときにトイレをつくったりしているわけですから、それを貸出しする制度をつくり、壊したら弁償してもらうというようなことにすればいいわけで、この147個の財産を活用しない手はないというふうに、これはお願いをして、答弁……。やりますか、どうぞ。
○教育政策課長 今147台を活用ということでございますけれども、私どもも、この147台のうちの一部を使いまして、同じ場所で3台で測定をいたしましたけれども、それぞれ3台が、また別の数値をあらわします。0.1マイクロシーベルトほどの誤差もあるということで、これが正確な数字をあらわすというふうに思えません。あくまでも、これは理科実験で大気中の放射線があるかというものに使うべきだというふうに考えております。
○針谷委員 全然だめだ。
○委員長 時間でございます。
○針谷委員 認識が狂っているよ。