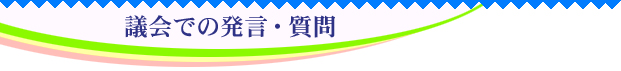■定例会一覧■
クリックすると各定例会の目次にリンクします
●2011年度
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2010年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2009年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2008年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2007年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2006年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2005年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2004年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2003年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2002年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
第2回足立区議会定例会
第1回足立区議会定例会
●2001年度
第4回足立区議会定例会
第3回足立区議会定例会
●学校統廃合、障がい者支援、ディーセント・ワーク等について−針谷委員(2011年10月13日)
○針谷委員 おはようございます。最後の質問でございまして、時間ありませんので、端的な答弁をお願いいたします。
まず、緊急の事態が起きましたので、予定外の質問ちょっとさせていただきます。
昨夜、世田谷区で弦巻地区の住宅街の歩道で、毎時2.71マイクロシーベルトの放射線量を検出したと世田谷区が発表しました。飯館村で12日に計測された2.05マイクロシーベルトよりも高い。区では、この原発事故で放出された放射性物質が雨水で運ばれて蓄積された可能性があるとしていますが、水で洗浄したけれども、数値は下がらなかったと。昨日、私が質問しました児玉龍彦東大アイソトープ所長の言う非線形という、予測がつかない場所で濃縮が起きるという指摘のとおりの事態になったんだろうというふうに思います。やはり区民の不安は一層拡大をすると思います。昨日学校にある放射線測定器を貸し出す問題であるとか、食材の検査などについて質問しましたが、やはり認識の違いが余りにもあるので、これについては、予告ということで、災害オウム特別委員会で、この見地から質問をいたしますので、よろしくお願い申し上げます。
教育委員会の暴走は許せぬ、統合協議会移行は開かれた学校づくり協議会を通じて
一昨日の浅子委員に対する学校教育部長の答弁であります。これは明らかに、議会と執行機関のルールを無視した、私は、教育委員会の暴走だろうと思っております。開かれた学校づくり協議会を通じて統合協議会を構成していくという方針は、我々議員に配られた、いわゆる適正規模の方針、適正配置の方針でも、明確に、開かれた学校づくり協議会を通じて統合協議会へ移行していくということが書いてあって、ただし書きで、部分的に統合に関係する地域の方々の推薦もカットするというふうに言っているんですが、もう鈴木学校教育部長の答弁というのは、明らかに、この開かれた学校づくり協議会を飛び越えてまで、統廃合、何がなんでも強行しようというようなものでありまして、自分たちが議会に提示したばかりの方針を勝手にねじ曲げても構わないという横暴を、私は許すわけにいかないというふうに思います。
学校教育部長、昨日の答弁を私は撤回すべきだと思いますが、いかがですか。
○学校教育部長 基本的な統合地域協議会の考え方は、今針谷委員ご指摘のとおりでございます。特に……。
○針谷委員 そういう説明は言わなくていいから、撤回すべきかどうか聞いているんです。
○学校教育部長 全く撤回するつもりはございません。
○針谷委員 私は、委員長、これは議会と執行機関に対する申合せでも、私は、反するんじゃないかと思うし、やはり議会軽視、議会無視だろうというふうに思うんです。委員会を休憩してテープを起こすなりして、これについては、この扱いについての協議をお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。○委員長 ただいま針谷委員から休憩を求める発言がありましたが、後刻、議事録を精査し、委員長において処置いたしたいと存じますので、ご了承願います。
○針谷委員 私は、これは、もう休憩して、この問題について、執行機関と議会との関係についても明らかにする必要があるというふうに思いますが、委員長から、そういうお話があったので、それについては従いたいと思います。
大きなハンディをもった視覚障がい者への負担を無くせ
障がい者施策についてお伺いします。
視力障がい者同行援護について、社会参加の一歩は外出であると、歩行の安全を、そして、安心、利便の確保が同行援護だろうと思うんです。視覚障がい者の歩行には、落ちるとか、ぶつかるとか、つまずくとか、迷うとかという危険と不安が常にありまして、とりわけ命の危険と背中合わせになっているのが、駅のホーム、横断歩道の歩行ということで、先日、障がい者団体の方々が、障がい福祉課長との要望でも、そのことが話されました。特に横断歩道の歩行においては、生活道路の交通信号機に音声が付加されていないために、横断歩道の場所や信号の色や渡る方向から、なかなか困難があるということであります。
そういう中で、ガイドヘルパーを派遣する移動支援事業、これについては、障害者自立支援法の見直しに当たって社会保障審議会は、重度の視覚障がい者の同行支援について、自立支援給付にするなど自立支援給付の対象を拡大することを検討すべきであるというふうに提言をして、それがやられたと。ここに位置付けることはいいんだけれども、この自立支援法の悪しき応益負担が持ち込まれて、課税者に対して1割負担が導入されたと。これについては、課税者といっても、視覚障がいという大きなハンディ、これに新たな負担を求めるというのは、私はノーマライゼーションの考え方に反すると。国会の請願でも、無料で実施をするように求めているんですが、区として何らかの措置を講じる必要があると思いますが、いかがでしょうか。
○障がい福祉課長 同行援護が自立支援法に移行しまして、自立支援法では、本人と配偶者に収入がある場合、一部負担が生じるということですが、ちょっと、収入があるということで、負担能力があるというふうに考えますので、特に考えておりません。
○針谷委員 実態をよく見てくださいよ。もう本当に大変ですよ。だって、仕事がある、収入があるといっても、大きなハンディがあるわけですから、収入だって、大した収入じゃありませんよ。そこをよく踏まえてください。
次に、芸術センター内の点字ブロックについてお聞きします。
芸術センターに向う区道には、黄色の点字ブロックがあります、区道は。ところが、芸術センターに入る広場とエントランスに入ると色がグレーになってしまう。これは前から芸術センターの問題として、いろいろ指摘されていますが、軽度の視覚障がい者は、この黄色の点字ブロックを頼りにハローワークなどに行っている。あそこにハローワークあるお蔭で、大変、視覚障がい者の方も多く通っているそうです。西新井のギャラクシティに向う環七の横断歩道、あそこもギャラクシティがあるので、多くの視覚障がい者が通うんですが、ここについては、まずハローワークに向う芸術センター前の点字ブロックのグレーを黄色に替えることと、西新井の環七の横断歩道を音声信号に変えるということについて、いかがかどうか。検討するか、しないかでいいですから、お答えください。
○中小企業支援課長 東京芸術センター内の物については、既に先週、口頭で事業者に伝えてあります。
○企画調整課長 環七の信号のところの音声装置ですけれども、区としまして、優先順位をつけて、今警視庁の方に協議をしているところでございます。 今後、交通マスター計画、総合交通計画を実施後に、バリアフリー化についても検討していく予定ですので、その中でも、区内全域合わせて検討していきたいと思っています。
視覚障がい者用のパソコンソフト購入費補助金増額を
○針谷委員 よろしくお願いします。
次に、視覚障がい者用のパソコンソフトですけれども、音声認識ソフトは大変高価なんですが、例えばマイワードというソフトがあるそうですが、8万円もすると。その他ソフトも大変高価で、区の助成があるということはいいことなんですが、10年間で10万円という制限がかかっている。今OSのバージョンアップ、皆さんもお使いになっているからご存じの話ですけれども、2000年から、この間、もう三つ、四つ、かわっていますよね。Meから2000、XP、セブンと、これかわるたびにセキュリティーが強化されて、前のソフトが使えないような状況になっているというふうに思うんです。
杉並区では、足立区の1.5倍の助成となっておりますし、他区は限度額20万円というようなところもあるんですが、これについては、限度額を上げるべきじゃないかと思っておるんですが、いかがでしょうか。
○障がい福祉課長 この視覚障がい者の情報通信支援用具の補助でございますが、21年から、この補助制度始まりまして、21年、22年と申請があるんですけれども、ちょっと今後は、財政的な影響もあるので、もう少し様子を見ていきたいと思います。
○針谷委員 これもやはり現実に合わないとなれば、是非改善してもらいたいと思います。
適正な仕事・権利・収入を保障するディーセント・ワークの確立を
次に、ディーセント・ワークの問題、お伺いをしたいと思います。
ディーセント・ワークっていうのは、適切な仕事、諸権利が守られ、妥当な収入を生み出す。この妥当な収入とは、子どもたちの将来や家族の老後も準備できる収入というのが、このディーセント・ワークと言われております。ILOは、このディーセント・ワークを強く提唱しておりますけれども、足立区の公務労働はどうなっているのかと。区の職員だけではなくて、指定管理者、委託、8,000名を超える区行政に携わる人たちのディーセント・ワークが確保されているのかをちょっと見たいと思うんです。
まず、土木の公園事務所、公園工事事務所の労働なんですが、ここは、すぐやる課と言われるような場だろうと思うんですが、先日の台風15号で区内の樹木が恐らく200本以上倒壊したと、なぎ倒された。道路に倒れた樹木を放置していることは危険ですから、区民からも相当な通報があり、私にもメールが来ました。この土木関係の職員さんは、夜中の2時、3時でも、いつでも飛び出して、これを直しに行くと。
実は、公園事務所は、東西南の三つに分かれていて、正規職員は三つの班に数名しかおりません。それ以外は民間委託。夜中の緊急対応も契約内容に含まれている。事例としては、道路の陥没、樹木の倒壊、河川の異常水位の経過観察、夜間巡回パトロール、苦情処理、いろいろな仕事やっている。正規職員は削られて、住民対応は間に合わないという事態、過労死の危険さえあるような状況を、私、聞いております。
例えば台風15号で河川の異常水位を見ている職員は、今回の台風は非常に遅かったので、警戒水位に入ってから寝ないで見なければならない。これが何日も続いたということで、夜中3時、4時まで見ていても、朝の8時には出勤しなきゃならないというような状況があると。しかし、また、夜中、緊急通報があって出かけても、移動時間に往復1時間ぐらいかかっても、これは超勤には認めないと、やった作業時間しか認めないというようなことにもなっているということですが、こういう実態があることを管理職の皆さんは聞いておりますか。
○みどりと公園推進室長 管理事務所の方から報告は受けております。
○針谷委員 それで、委託業者で働く職員の待遇は、もっと深刻なんです。賃金は区職員の半分以下、事故を起こせば、すぐにいなくなっちゃうそうです。どうしてかと言うと、多分、転勤か解雇、こういうことがあると。まさにノー・ディーセントだろうと思うんです。こういう実態については、やっぱり是非改善をしてもらいたいというふうに私は思っておりますけれども、今回、区議会に陳情が出されております。
一つ一つ、聞いていきたいと思うんですが、まず、契約の改善です。
区内の公共工事については、これまで、落札率が低ければ低いほどいいという悪しき不公正な過当競争が続いてきました。今回、区が新たな措置をとって改善されたと、私も思います。若干この区の対応が早かったために、いろいろな矛盾も出たというのが、この間のどなたかの質問でありましたけれども、しかし、これは、私はいいことだろうと。最低価格の引上げや予定価格の事前公表を見直すという、求める声も広がっておりますけれども、これについてのやはりそういった適正な公共工事、そして、そこで働く人の労働条件を確保すると、そういう改善をするということについては、総務部長、どうでしょうか。
○総務部長 今ご質問のありましたディーセント・ワーク、働きがいのある、また生きがいを持って働ける、そういった労働環境あるいは労働条件を整えるのも、足立区の仕事だというふうに、私、思っております。したがって、先ほどご案内のあった品質の確保をしながら適正な競争が行われるような、例えば最低価格の引き上げであるとか、制限価格の見直しであるとか、こういったことも積極的に、これまで進めてきております。これからも、そういったところについて、英断を持って進めていきたいと、このように考えています。
○針谷委員 それで、建設業協会、その他、これは全党に要望されていることだろうと思うんですけれども、予定価格の事前公表の見直し、これも必要かなというふうに思っているんですが、これについては、いかがでしょうか。
○総務部長 予定価格の公表というのは、談合でありますとか汚職の防止という意味で入れられてきたわけですけれども、この弊害もあるというふうに、私、感じておりまして、まだ23区も東京都も踏み切っていないわけですけれども、この予定価格の公表についても、一定の議論の上でどうすると、公表すべきなのか、続けるのか、続けないのかを、きちっと決めていきたいと、このように考えて、問題意識としては、私、持っております。
○針谷委員 やはり良質な公共工事の確保と働く者の現在の労働条件を確保するということは、非常に重要なことなんで、是非、これは積極的に進めていただきたいというふうに思っております。
その一つの手法として、公契約条例があります。公共工事の現場で働く全ての労働者に対して、賃金の最低基準額を条例により保障するであるとか、良質な公共工事を確保する。行き過ぎた過当競争を是正するため野田市が実施をして、今度は、政令指定都市で初めて川崎市が行うということになりましたけれども、先日、都政新報に野田市長がインタビューに答えておりまして、私も読みました。これについては、特に契約関係が重層化、複雑化している建設業、そして、経営規模が小さい、特に足立区、経済の循環をしていくという点でも、公契約条例が特に私は必要だろうというふうに思っております。
まず、公共部門からルールを守り、労働条件が向上されるように、一定の規制と誘導を行うことが必要であり、公契約条例の制定により労働者の権利と公正な労働条件を確保することが重要だというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
○総務部長 私も、その趣旨には賛同いたしますし、そのとおりだというふうに思います。特に、役所の契約だけでいいのか、あるいは国の仕事でありますとか、全国の自治体でどうなっているのかということがあります。これは、私は、最終的には公契約基本法のようなものになって、それに基づいてやるべきだと、法律で規制をしていくべきだと、このように考えておりますけれども、その先駆的なことを条例でやっていくと言うところにも、私は、意味があるというふうに思います。
ただ、内容的には、その最賃法の最低賃金の引上げだけでいいのか、あるいは品質確保に対して評価する手法をどうするのか、あるいは適正な価格の範囲内で適正な競争を行うという地方自治法の理念がありますけれども、そういったものを、こういったものを含めた、私は、ルールを足立区なりに発信していきたいと、このように考えておりまして、その先に公契約条例があるんではないかなと、このように考えております。
○針谷委員 それ、是非私はやっていただきたいと思っております。
地域経済活性化につながる住宅改良助成制度の拡充を
時間がないので、最後の質問に入りますが、建設産業というのは、2007年の建築基準法改正以来、長期不況に見舞われて疲弊の度合いを一層深めており、廃業や離職が後を絶ちません。地域住宅産業は、元来、裾野が広い経済波及効果を持っている産業であろうと思うんです。また、地域の経済活性化にとっても重要であります。今、まさに地域経済循環策を拡充するということが必要だろうというふうに思っております。地域住民が住宅や店舗を改修することによって、そのまちに住み続ける、営業を続けることでまちの経済が回り、ひいては自治体の活性化、税収増にもつながるということで、これは全国の自治体で広がっているところであります。
区は、これについては、これまでずっと実施をしないという答弁をしてきましたけれども、私は、個人への資産の公費投入に関する是非についても、国土交通省の見解では、公費投入を否定することに対しては、一切今は一般的でないと。住生活基本法の中にも、住宅は社会的性格を有するとしていて、日本経済連でも、住宅が社会的資産であるというふうに位置付けております。したがって、住宅によるリフォーム助成というのは、地域住民への初期投資が大きな経済効果、有効性があるというふうに思います。
この足立区でも、住宅改良助成を環境、耐震、高齢者などに対応した助成制度として一定あります。しかし、これは狭められているということで、区民にとって使いやすい制度として、是非早急な制度の拡充を求めたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○建築調整課長 住宅改良につきましては、いろいろな目的がございます。主に性能をグレードアップする耐震とかバリアフリー、それと、もう一つは……。
○針谷委員 説明聞いているんじゃないんだよ。全然わからない。
○建築調整課長 増改築、間取り、あるいはメンテナンスがありますが……。
今のところ、建築室の方におきましては、段差解消あるいは手すりの設置関係を限定しております。
○委員長 時間です。
○針谷委員 冷たいね。